マイナーな部活動
うちの子どもは弓道部に入っています。
下積みの練習期間は結構長く。
入学してから夏休み前まで筋トレやゴムでの練習が主で、弓道場で弓矢を構えて矢を放つ、建前には立たせてもらえず、もっぱら筋トレやお米の米俵のような巻藁(まきわら)を的にして練習していました。
わたしは今まで弓道とは縁がなかったので内情をよく知りませんでした。
ただ、高校の頃、たまに見かける袴を着た道着は男子も女子も凛としてかっこいいな、と思っていたくらい。

新しい発見が
まさか、子どもの部活の様子を通して、日本の文化に少しずつ触れていくようになるとは。
新しい発見がいくつかあります。
一つ目。
学校の弓道場には、神棚があるそうです。毎日きちんと誰かがお供え物や榊を取り替えたり、お参りしたりしているかは謎。
二つ目。
弓にかける弦。大麻の繊維でできています。大麻草の繊維はとても丈夫で、戦前は日本のどこでも手に入りやすいものだったのでしょう。
三つ目。
座禅を組む。瞑想をする。

精神統一
当然ですが、弓を引いて的に当てる、一連の動作は精神統一が欠かせません。
通常4本続けて矢を射るのですが、最初の一本目が外れたからといって、そこから気分が沈んでしまってはいけない。
逆もまた然り。的に命中したからといって有頂天になってしまってはいけない。
気持ちを常に平常に保つ。大人でも難しい。
そのために、練習時間内に座禅があるそうで。
呼吸に意識を集中して、1分間に3回長い息をする。ただただ吸う息と吐く息に意識を向ける。それを5分くらい続ける。

なんで、それするの?

気持ちを落ち着かせるの。
心がざわざわしてたら、当たるもんも当たらんから。
今やってる動作に集中するように。
子どもの言葉にはっとしました。
こころがざわざわしていることが通常運転のようになっている、わたしたち。
ざわざわとした気持ちを落ち着かせよう。今に意識を集中しよう。
逆輸入される古き良き日本のもの
剣道、柔道、書道とあわせて、弓道などの「道」がつく日本の文化は、戦後GHQにより学校教育では禁止されていました。それだけ、日本人の精神性に通じる恐るべきものだったのでしょう。
日本人の精神性に通じる禅。欧米でもマインドフルネス瞑想などと呼ばれ、多くの人々や大きな企業に受け入れられています。
今まで日本の座禅とマインドフルネス一緒じゃないの?と思っていました。でも、よく調べると少し違いがあるようで。
座禅はその効果を期待するものではなく、マインドフルネスとは瞑想状態を経験することにより、その先の業務の効率化や良好な健康状態を保つなど見返りを期待するものである、という説明を見かけ、なるほど、と納得しました。
マインドフルネス瞑想は多くの企業で取り入れられていて、それが高い効果を期待していて、その通りの効果が出ている、ということはとても良くわかります。
日本の良さを見直そう、取り戻そう
日本人は古来から、舶来のものを重宝する、自分達よりも優れたものだと取り入れることがDNAに組み込まれています。
「座禅を組む」という言葉より「マインドフルネス瞑想」という方がおしゃれに心地よく聞こえるし、効果がありそう。と思ってしまうのも仕方ないのですね、きっと。
その後の効果を期待しすぎるのは良くないけれど、心がざわざわしない「今ここに在る」状態になれることはとても良いこと。

毎日3分でもいいから取り入れましょう。椅子に座ったままでいいから。
そして、この座禅の瞑想、弓道部だけじゃなくて、学校全体で実施してほしい。いや、社会全体でやってほしい。と思ったのでした。
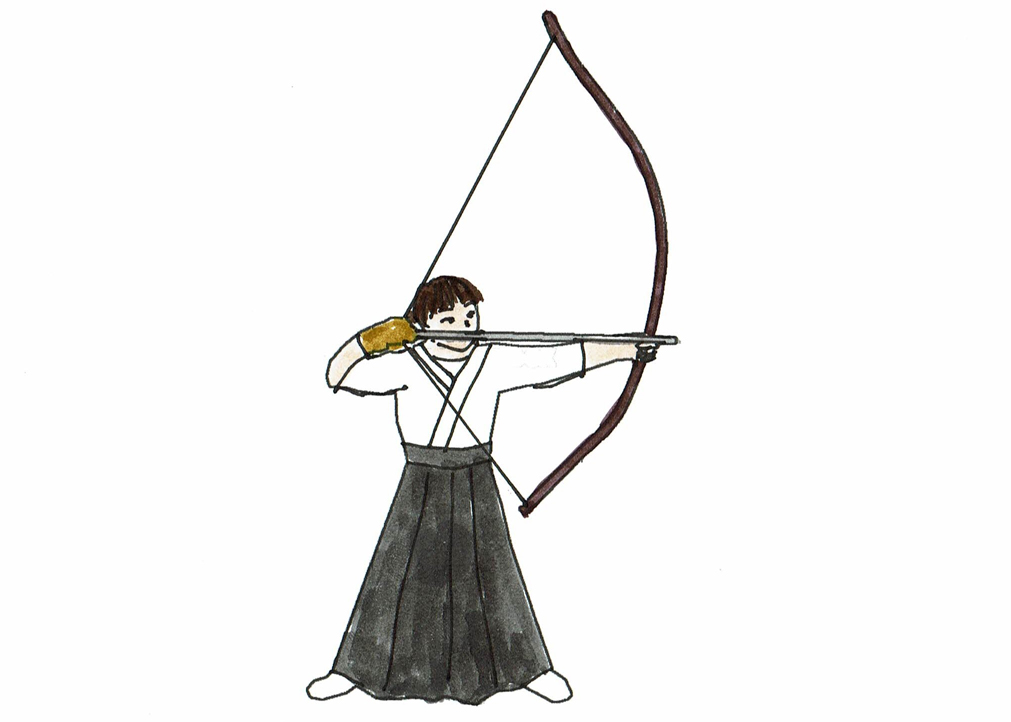
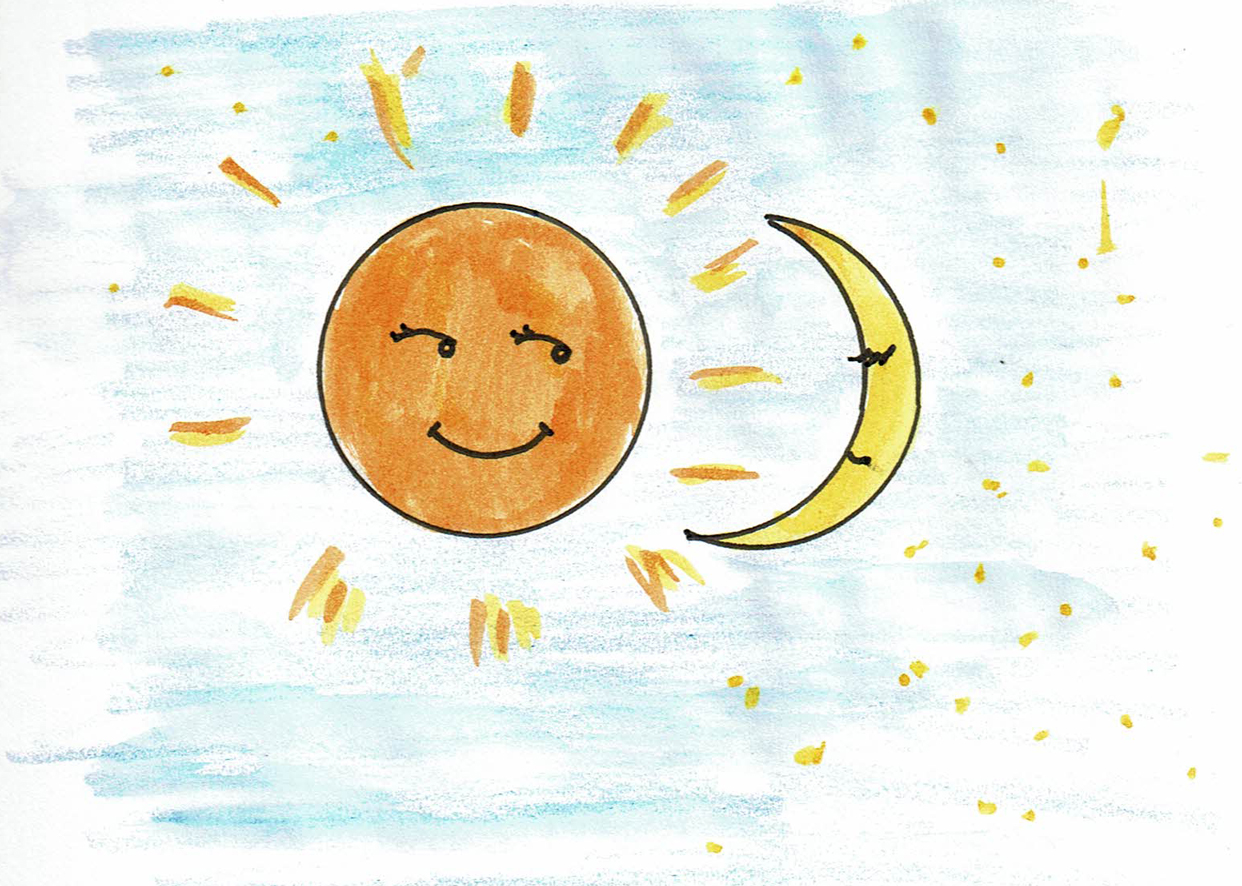
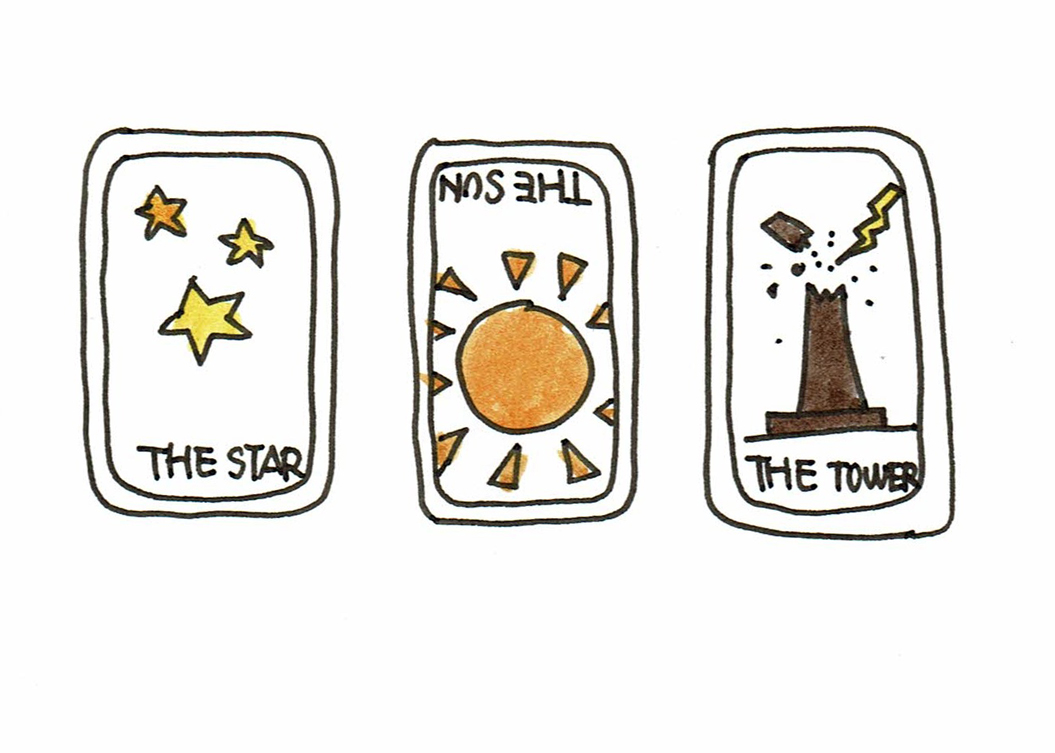
コメント